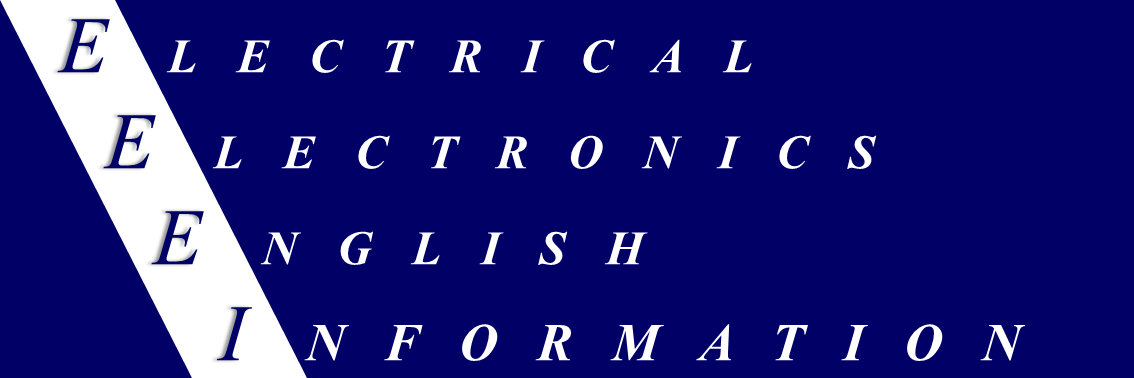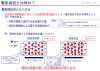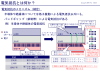本日のスライド
PCの場合、「スライド表示」を別タブで表示して画面の左右に記事とスライドを表示しながら見ることをお勧めします。
スマホの場合は、スライドを一通り読んでから記事を読むと理解がしやすいかと思います。
スライドはpdfでダウンロードできますので商用利用目的を除いてご自由にご使用ください。
電気抵抗のメカニズム(P. 1 ~ P. 2)
電気抵抗の発生理由
「電気抵抗=電子の移動量を少なくする要因」です。
ここでの移動量とは、「一定方向への電子の平均移動距離×電子の数」のことを表しております。つまり、物質内の電子の進んだ距離の総和のことです。
電気抵抗が発生する(電子の移動量が少なくなる)理由は、主に下記の2点があります。
- そもそも自由電子の量が少ない
- 格子の熱振動による電子の移動の妨げ
①について
各物質に依存しており単位体積当たりの自由電子の数に依存します。
自由電子が少ないということは、その分自由電子の移動量が減り、電気も流れにくくなることになります。
②について
温度が上がると、物質内の格子の熱振動が激しくなります。
その熱振動が大きくなることにより、自由電子の移動が妨げられてしまう(散乱してしまう)ことが電気抵抗の増加につながります。
一方、物質の温度を極低温まで冷やすと格子の熱振動が落ち着きます。そうすると自由電子は移動を妨げられないので、電気抵抗は低下していきます。
補足
超伝導体というものがあります。
これは、極低温まで冷やすと電気抵抗が極めて小さくなる物質のことです。
ここでの極低温とは、絶対零度(-273.15℃)近い温度のことです。
最近は、高温超伝導体の研究も活発に行われており、液体窒素温度(-196℃)で超伝導状態となるものを利用した実用研究が活発に行われています。
自由電子について、詳細に知りたい方は下記の記事を参照してください。
https://eeei-bulletinboard.com/electrical_electronics/article_1/半導体・絶縁体の電気抵抗
半導体や絶縁体では、上記2つの電気抵抗要因に加えて「バンドギャップ(禁制帯)による電気抵抗」が存在する。
半導体、絶縁体は物質内部で①価電子帯、②禁制帯、③伝導帯の3つの領域で分けることができる。それぞれの領域の特徴について下表にまとめる。
| 価電子帯 | 多くの電子が存在する領域。 電子で満たされているため自由電子の移動はできない一方、 正孔は移動することができ、この領域では正孔の(見かけ上の)移動により電気が流れる。 |
| 禁制帯 | 電子の存在できない領域。 存在できないので、価電子帯→伝導帯へ移る電子はこの領域を飛び越えていく |
| 伝導帯 | 電子が自由に移動することができる領域。 この領域の電子は自由電子となり、電気伝導に寄与する。 |
価電子帯の電子が、電圧や光、熱などのエネルギーを受けて伝導帯に禁制帯を飛び越えて励起されることで、自由電子となり伝導帯内部を移動し電気の流れに寄与することになります。
よって、半導体・絶縁体の場合はこの禁制帯を飛び越えるエネルギーが電気抵抗を構成する要因のなかで大きく寄与しているため、温度が高いほど電気抵抗が小さくなる傾向がある。
電気抵抗の導出(P. 3 ~ P. 5)
電気抵抗の公式
電気抵抗の公式は下記となる
\[R=\rho\frac{l}{S}=\frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}\]
| 記号 | 単位 | 説明 |
| \[R\] | \[\Omega\] | 電気抵抗 |
| \[l\] | \[m\] | 物質の長さ |
| \[S\] | \[m^2\] | 物質の断面積 |
| \[\rho\] | \[\Omega m\] | 物質の抵抗率。物質ごとの電気抵抗を示す物理量 |
| \[\sigma\] | \[1/\Omega m\] | 物質の導電率。物質ごとの電気の流れやすさを示す物理量 |
ポイント
公式が出てきたときは、丸暗記はやめて定性的な特性と結び付けて式を導出できるようにしましょう。
例えば、上記式では断面積が大きい(S↑)
→抵抗が小さくなる(R↓)
→Sは分母長さが長い(l↑)
→抵抗は大きくなる(R↑)
→lは分子
電気抵抗率
電気抵抗率とは、各物質ごとに固有の電気の流れにくさを表す物性値のことです。
抵抗率が大きい物質 → 電気が流れにくい
抵抗率が小さい物質 → 電気が流れやすい
という特性を示します。
一方、導電率とは、各物質ごとに固有の電気の流しやすさを表す物性値のことです。
抵抗率の逆数で与えられます。
導電率が大きい物質 → 電気が流れやすい
導電率が小さい物質 → 電気が流れにくい
まとめると
| 大きい | 小さい | |
| 抵抗率 | × | ○ |
| 導電率 | ○ | × |
(○:電気流れやすい、×:電気流れにくい)
電気抵抗の温度特性
導体についての電気抵抗の温度特性については下記の式が一般的に知られています。
\[R_{T} = R_{T_{1}}\{1+\alpha(T-T_{1})\}\]
| 記号 | 単位 | 説明 |
| \[R_{T}\] | \[\Omega\] | 現在温度\(T\)での電気抵抗 |
| \[R_{T_{1}}\] | \[m\] | 基準温度\(T_{1}\)における電気抵抗 |
| \[\alpha\] | \[m^2\] | 基準温度\(T_{1}\)における温度係数 |
| \[T_{1}\] | \[\Omega m\] | 基準温度 |
| \[T\] | \[1/\Omega m\] | 現在温度 |
基準温度は一般的に20℃が使用されることが多く、各金属の20℃における温度係数の情報が入手できます。
電気抵抗器の種類(P. 6 ~ P. 7)
機能の種類
電気機器で使用されている電気抵抗器ですが、各機能から主に下記に分類することが可能です
- 固定抵抗器
- 半固定抵抗器
- 可変抵抗器
- シャント抵抗器
①固定抵抗器について
その名の通り抵抗値が固定されている電気抵抗を指します。
電気機器で使用されているものの多くは固定抵抗器です。
②半固定抵抗器
抵抗を変更することができる抵抗器ですがあるが、電気機器を使用するユーザが操作することを意図していない抵抗器になります。製造者側でのみ調整される抵抗器です。
③可変抵抗器
抵抗を変更することができる抵抗器。ユーザが操作することを意図してつけられている。
④シャント抵抗器
電流を計測するための抵抗器。抵抗値が小さく、両端に計測用のタップが備わっています。
構造や抵抗体の種類
電気抵抗を構成する抵抗体の種類は、主に下記のようなものがある。
- 炭素被膜抵抗
- 金属皮膜抵抗
- 酸化被膜抵抗
- 巻線抵抗
- セメント抵抗
- メタルクラッド抵抗
①炭素被膜抵抗について
最も一般的な汎用抵抗器。価格が非常に安いが、抵抗誤差が大きく温度特性もよくない
②金属皮膜抵抗について
厚膜型と薄膜型で分けることができる。
金属を抵抗体に使用しているため温度特性が良好で抵抗値の誤差も少ないのが特徴。
一方で、炭素被膜抵抗に比べると価格が高い。
③酸化被膜抵抗について
小型で中電力(1W~5W)を扱える抵抗器。耐熱性が高い特徴がある。
一方で、高価である。
④巻線抵抗
抵抗体としてらせん状の金属線を用いたもの。温度特性、耐熱性、中電力を扱える。
一方で、インダクタンス成分を含むため高周波に対して不向きであり高価である。
⑤セメント抵抗
大電力(2W~20W)を扱える抵抗器。巻線抵抗の絶縁性、耐熱性をセメントでモールドすることで高めたもの。
一方で、インダクタンス成分を含むため高周波に対して不向きであり高価である。
⑥メタルクラッド抵抗
大電力(>2W)を扱える抵抗器。巻線抵抗に絶縁の上で金属外装を装着させ、さらに放熱板を備えたもの。
インダクタンス成分を含むため高周波に対して不向きであり高価、扱う電力にもよるがサイズが大きくなる。
まとめ
今回の記事では、電気抵抗についてそのメカニズムや各公式、実際に使用される抵抗の種類について解説させていただきました。
- 電気抵抗とは、電子の移動量を少なくする要因のこと
- 導体の場合は、電子の量や温度が電気抵抗に影響を及ぼす
- 半導体・絶縁体の場合は、上記に加えて禁制帯のギャップが電気抵抗に影響を及ぼす
- 電気抵抗は抵抗率、導体の面積、長さから導出ができる
- 導体の場合は、温度と抵抗値が正の相関があり、一般式が定義されている
- 抵抗器の機能の種類には、固定抵抗器、半固定抵抗器、可変抵抗器、シャント抵抗器が主にある
- 抵抗器で使用されている抵抗体の種類には、炭素被膜抵抗をはじめとして様々な種類があり、それぞれ用途が異なっている。